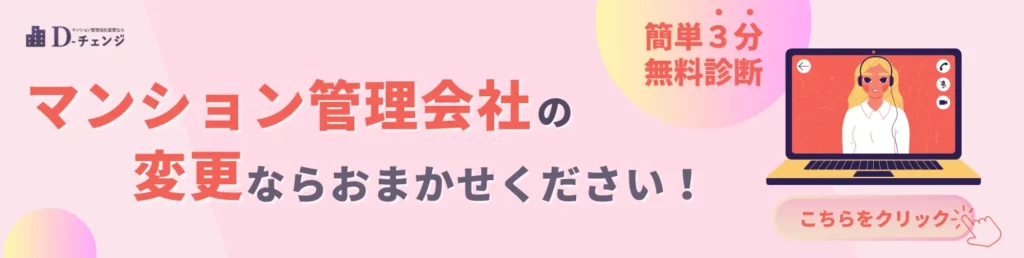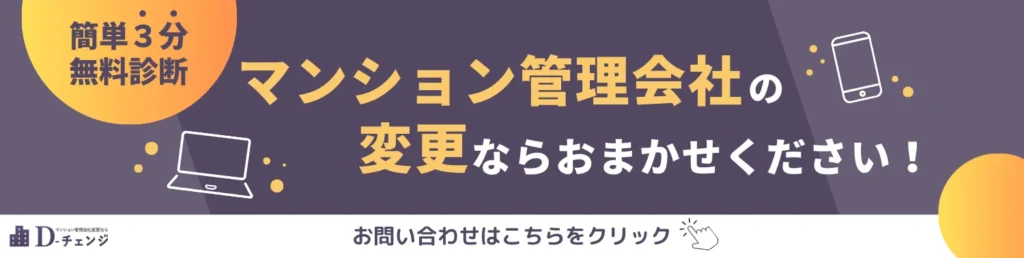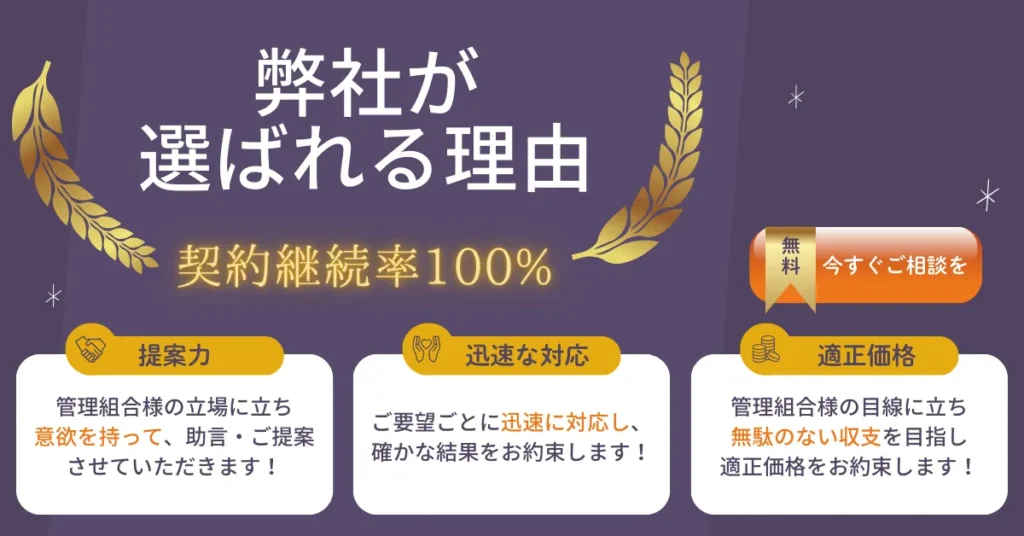築70年のマンションも売却は可能!|売却するコツや耐用年数についても解説
- 「築70年のマンションって売却できるのかな……」
- 「築70年のマンションを高く売るコツが知りたい」
- 「なんでマンションの建て替えって少ないのかな?」
このような悩みを解決できる記事となっています。
結論、築70年のマンションも売却は可能です。
本記事では、築70年のマンションを売却するコツやマンションの建て替えが少ない理由について解説します。
最後まで読むと、売却するコツがわかり、高く売れます。

この記事の監修者
株式会社デュアルタップコミュニティ 代表取締役社長
池田 秀人
2017年6月株式会社デュアルタップ入社、2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、完全子会社へ(取締役就任)、2019年7月専務取締役に就任、2020年7月代表取締役に就任~現在に至る
所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
目次
築70年のマンションも売却は可能

結論としては、築70年が経過しているマンションも売却できます。
しかし、何も問題がない築浅マンションと同様に売却できるかというとそうではありません。
この記事では、築70年のマンションが簡単に売却できない理由を詳しく解説するので参考にしてください。
築70年のマンションが簡単に売却できない理由

築70年のマンションが簡単に売却できない理由は以下のとおりです。
- 旧耐震基準で建てられているから
- 管理組合の実態がない場合がある
- 修繕積立金が高い
- 建て替えが近いと思われる
- 立地が悪い
順番に解説します。
【理由①】旧耐震基準で建てられているから
築70年のマンションが売れにくい理由の1つに「耐震基準の観点」があります。
耐震基準とは、一定レベルの強い地震が来ても建物が倒れない耐性を持っているかどうかの基準で、建築基準法に定められています。
建築基準法は1950年に制定された以降、1971年と1981年、2000年に大幅な改正がありました。
1981年の改正前の耐震基準を「旧耐震基準」、改正以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼びます。
旧耐震基準では「震度5強程度の地震で損傷を受けないこと」と定められていました。
新耐震基準では、「中規模の地震でほとんど損傷しない、かつ、大規模の地震で倒壊・崩壊しない」という基準に改正されました。
【理由②】管理組合の実態がない場合がある
築70年のマンションは、管理組合の実態がない、機能していないなどの理由から、マンションの管理が行き届いていないことがあります。
現代では、建物の区分所有等に関する法律により、管理組合の規定が義務化されていますが、義務化以前は管理組合の規定は義務ではありませんでした。
管理組合はあるけど、組合員の高齢化によって、適切に機能していないこともあります。
管理組合として、機能していなければ、清掃業者の手配などがされず、マンションのエントランスや共用部に清掃や維持・管理が行き届かなくなります。
マンション購入者が内覧に来たときに、共用部分が汚れていたり、適切な修繕がされていない場合には購入希望者が現れにくくなってしまうでしょう。
【理由③】修繕積立金が高い
マンションの築年数が経過するにつれて、修繕や清掃などの管理にかかる費用が増加する傾向があります。
そのため、修繕積立金が高額になりやすくなります。
修繕積立金は、建物の修繕に充てられる費用で、マンションの所有者が毎月負担するものです。
築年数が古いマンションでは修繕費用が多くかかるため、積立金も増える傾向にあり、この点が購入希望者の興味を低下させる要因となることがあります。
【理由④】建て替えが近いと思われる
築70年を超えるマンションは、国が定める耐用年数を大きく上回るため、「建て替えが必要になる可能性が高い」と見なされます。
このため、購入者は敬遠する傾向にあります。
建て替えが実際に行われると、買主は建て替え費用の一部負担や、仮住まいへの移転費用など、追加の経済的負担を背負うことになるからです。
築70年を経過したマンションの購入は、近い将来における建て替えの可能性を考慮する必要があり、この点が購入希望者の関心を減少させる主要な理由となります。
【理由⑤】立地が悪い
中古マンションを売却する際には、その立地条件が成功を左右する大きな要因となります。
特に、周辺の利便性や住みやすさは、土地の価値と並んで購入希望者にとって重要なポイントです。
例えば、「近くにショッピング施設が揃っているか」や「子育て環境が整っているか」といった条件は、多くの買い手にとって大きな魅力となります。
反対に、必要な生活施設へのアクセスが悪いなど、日常生活に不便を感じるようなエリアでは、マンションの需要が低くなり、売却が難しくなる場合があります。
マンションの耐用年数

マンション(鉄筋コンクリート)の法定耐用年数は、47年と定められています。
これは毎年減価償却していき、最終的に償却がゼロになるのが47年ということです。
耐用年数を超えると性能が落ちるように思われがちですが、耐用年数=寿命ではありません。
鉄筋コンクリート以外の住宅用の耐用年数表は以下のとおりです。
| 構造・用途 | 耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造 | 22 |
| 木骨モルタル造 | 20 |
| れんが造・石造・ブロック造 | 38 |
| 金属造 | 19〜34(大きさによって変動する) |
マンションの平均寿命

国土交通省の資料によると、鉄筋コンクリート(RC)造の建物の平均寿命は、約68年とされています。
この平均寿命は、自治体が管理する土地や建物などの台帳(固定資産台帳)にあるデータを参考に算出された数字です。
参照:国土交通省「期待耐用年数の導出及び外装・設備の更新による価値向上について」
築70年のマンションを売却するコツ

築70年のマンションを売却するコツは以下のとおりです。
- 築古物件も取り扱い可能な不動産業者を選別する
- 築年数に見合った価格で売る
- ホームステージング
順番に解説します。
築古物件も取り扱い可能な不動産業者を選別する
不動産売却を検討する際の第一歩は、専門の不動産業者による物件の査定を受けることです。
特に、築70年のような築年数が古いマンションの場合、その特性を理解し、適切に取り扱える不動産業者を選ぶことが成功への鍵となります。
なぜなら、不動産業者には得意とする物件のタイプがあり、築古マンションの売却経験が豊富な業者を選択することで、より適正な査定価格の提案や、スムーズな売却プロセスを期待できるからです。
築70年を超えるマンションの売却を考えている場合は、事前に不動産業者のホームページを確認し、築古物件の取り扱い実績を持つ業者に相談することをお勧めします。
築年数に見合った価格で売る
築70年のマンションを販売する際には、築年数を踏まえた適正な価格で市場に出すことが非常に重要です。
不動産価格は通常、同じ地域にある似た条件の物件を参考に決定しますが、築70年という長い経年は特別な配慮を要するポイントです。
築年数が浅い物件と同じ価格設定では、購入希望者を見つけるのは難しいでしょう。
そのため、売却価格を決める前に、複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された価格の根拠を詳しく確認することが大切です。
こうしたプロセスを経て、築70年の物件に適した価格を慎重に設定することをおすすめします。
ホームステージング
ホームステージングとは、販売中のマンションをモデルルームのように整え、購入希望者に物件の魅力をアピールする手法です。
インテリアを工夫することで、住まいの利便性や雰囲気を具体的に伝えることができ、マンション売却の際によく活用されています。
ホームステージングの主な利点は以下の通りです。
- 内覧者数の増加
- 売却までの期間短縮
- 売却価格の下落防止
一方で、デメリットとして挙げられるのはコストがかかる点です。
マンションを魅力的に演出するために、新たに家具やインテリアを購入する場合があります。
そのため、予算に合わせて計画的に進めることが重要です。
また、購入した家具の搬入や搬出時には、物件に傷や汚れをつけないよう細心の注意を払う必要があります。
マンションの建て替えが少ない理由

マンションの建て替えが少ない理由は以下のとおりです。
- 費用の負担が重い
- 建て替え決定までの流れが複雑
- 既存不適格な分譲マンションが多い
順番に解説します。
【理由①】費用の負担が重い
マンションの建て替えが進まない主な原因は、高額な建て替え費用の負担にあります。
管理組合による修繕積立金の蓄積があるにもかかわらず、その金額だけでは建て替えに必要な費用を賄うことが困難で、多数のマンションが資金不足により建て替えを断念しています。
一方で、建て替えに成功しているマンションの例もあり、これらは追加の分譲を創出し、その販売から得た収益を建て替え資金として活用しています。
たとえば、既存の100戸のマンションを建て替えて150戸に増やし、その新たに50戸を販売することで、必要な資金を確保しています。
しかし、新たなユニットの創出が可能なのは、土地の容積率に余裕があるマンションに限られる点に注意が必要です。
【理由②】建て替え決定までの流れが複雑
マンションの建て替えが難航する大きな理由の1つは、その決定プロセスの複雑性です。
マンション建て替えには、「建て替え決議」と呼ばれる、区分所有者及び議決権者の5分の4以上の賛成が必須です。
この賛成率の達成が最初の大きな障壁となります。
加えて、建て替え実施には、所有者が一時的に別の住居に移る必要があり、修繕積立金の増額など経済的負担も伴います。
特に、収入源が限られる高齢者が多い古いマンションでは、この経済的負担が合意形成の妨げとなりがちです。
結果として、多くのマンションで建て替え決議が取れず、管理組合も建て替えを推進しない方向に傾くことが一般的です。
【理由③】既存不適格な分譲マンションが多い
建て替えにおける課題の一つとして、既存の分譲マンションが現行の建築基準に適合していない場合が挙げられます。
具体的には、容積率の観点から不適格な状態にある物件が存在します。
例えば、容積率200%の指定がある土地で既に250%の容積率を使用している物件は、既存不適格と見なされます。
さらに、容積率規定が設けられる前に建設された物件の中には、現在の基準を超える容積で建てられたものもあります。
ただし、容積オーバーでなくても、容積率に余裕がない場合、建て替えは困難です。
これは、法令を遵守している建物であっても、容積率が完全に消化されている場合には、新たな建物に対して余地がないためです。
例えば、土地の容積率が300%で、現在の建物もその容積率をフルに使用している場合、建物は法的に問題ないものの、建て替えに際しては新たな課題が生じます。
マンションの寿命の要素

マンションの寿命の要素は以下のとおりです。
- 構造
- メンテナンス状況
- 立地
- コンクリートの質
順番に解説します。
構造
マンションが新耐震基準を満たしているか、旧耐震基準のままかは、その寿命に大きな影響を与えます。
旧耐震基準では震度5強程度の地震で建物が崩壊しないことを想定しているのに対し、新耐震基準は震度6強から7クラスの地震でも倒壊しないような耐震性が求められています。
新耐震基準は1981年に施行されましたが、それ以前に建てられた旧耐震基準の建物では、震度6強以上の大地震で倒壊するリスクが高まります。
そのため、旧基準のマンションは新耐震基準を満たすマンションに比べ、相対的に寿命が短くなる傾向があります。
マンションの耐久性を見極める際には、まず新耐震基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。
メンテナンス状況
マンションが適切にメンテナンスされているかどうかは、その寿命に大きく影響します。
定期的なメンテナンスが実施されているマンションであれば、買主も安心して購入を検討できます。
しかし、長い間メンテナンスが行われていないマンションは、買主にとって好印象を持たれにくいでしょう。
特に築年数の古いマンションでは、長期修繕計画が策定されていない場合があり、劣化や破損が放置されているケースも見られます。
このようなマンションは、メンテナンス不足により劣化が進みやすく、結果として寿命が短くなる傾向があります。
また、マンションの維持管理の中で特に重要とされるのが配管のメンテナンスです。
高度経済成長期の1960~1970年代に建てられたマンションでは、配管に問題を抱えているケースが多いと指摘されています。
配管の寿命は一般的に30年程度とされているため、それを超えた場合は新しいものに交換することが必要です。
立地
マンションの立地や周辺環境も、その寿命に大きな影響を与えます。
例えば、日当たりが悪いマンションは湿気が溜まりやすく、カビの発生や配管の腐食が進むことで寿命が短くなる可能性があります。
さらに、海に近い場所に建つマンションは、塩害の影響でコンクリートの劣化が通常より早く進むことが考えられます。
長く快適に住めるマンションを選ぶには、建物の状態だけでなく、立地条件もしっかりと確認することが大切です。
コンクリートの質
コンクリートは、時間が経つにつれて大気中の二酸化炭素が内部に侵入し、アルカリ性から中性へと変化する「中性化」が進行します。
この中性化が進むと、マンションの鉄筋部分が腐食しやすくなります。
特に、質の低いコンクリートが使用されている場合、中性化が早まり、鉄筋の腐食が進行しやすくなる可能性があります。
さらに、外壁や廊下のひび割れが早い段階で目立ち始めることもあり、結果的にマンションの寿命を短くする要因となります。
近年では、大規模修繕を必要とせず100年持つとされる高強度コンクリートを使用したマンションも増えています。
長く快適に暮らせるマンションを選ぶには、コンクリートの質にも注目することが重要です。
築70年のマンションを放置してはいけない理由

築70年のマンションを放置してはいけない理由は以下のとおりです。
- 廃墟になってしまう
- 建て替えで再購入か引っ越しを求められる
順番に解説します。
廃墟になってしまう
築古マンションでは、管理組合が存在しない、または機能していない場合、管理や清掃が行き届かず、放置されると廃墟化するリスクがあります。
物件が廃墟化すると、不法投棄などの被害を受けやすくなりますが、管理組合がない場合、投棄されたゴミを片付ける人もおらず、問題が放置されることになります。
さらに、廃墟化が進むと害虫が発生しやすくなり、住環境が悪化して住民が離れていくのはもちろん、新たな購入希望者も現れにくくなります。
その結果、物件の売却価格はどんどん下がり、負のスパイラルに陥る可能性があります。
こうした状況になると、資産価値は急激に下落するため、売却を検討するなら早めに行うことで利益を確保しやすくなるでしょう。
建て替えで再購入か引っ越しを求められる
築70年のマンションは寿命が長くないため、近い将来建て替えが必要になる可能性が高いです。
その場合、再取得するか転居するかの選択を迫られることになります。
いずれを選んだとしても、現在のマンションに住み続けることはできず、引っ越しのために費用や手間がかかるのは避けられません。
新しい生活環境に慣れるまで精神的な負担を感じることもあるでしょう。
建て替え費用は通常、管理組合が毎月徴収している修繕積立金で一部賄われますが、積立金だけでは足りず、不足分が所有者に追加で請求されるケースが一般的です。
この追加費用は数百万円から、場合によっては数千万円と非常に高額になるため、支払えない場合は転居を選び、マンションを売却する必要が生じることもあります。
ただし、建て替えが決まってからマンションを売却する際には、リフォーム費用を差し引いた金額での売却になる可能性があるため、注意が必要です。
まとめ【築70年のマンションも売却できる】
今回は、築70年のマンションを売却するコツやマンションの建て替えが少ない理由について解説しました。
築70年のマンションを売却するコツは以下のとおりです。
- 築古物件も取り扱い可能な不動産業者を選別する
- 築年数に見合った価格で売る
「マンション管理会社変更したいけど、やり方がわかんない……」
「今のマンション管理会社に不満がある……」
こういった悩みはありませんか?大切なことなので慎重になり、なかなか自分では動けませんよね。
弊社、株式会社デュアルタップコミュニティでは、管理会社の業務を知り尽くしたコーディネーターが適切なマンション管理をご提案致します。
今ならマンション管理会社変更についての無料相談・3分無料診断を行なっています。
相談は無料なので気軽にお問い合わせください。