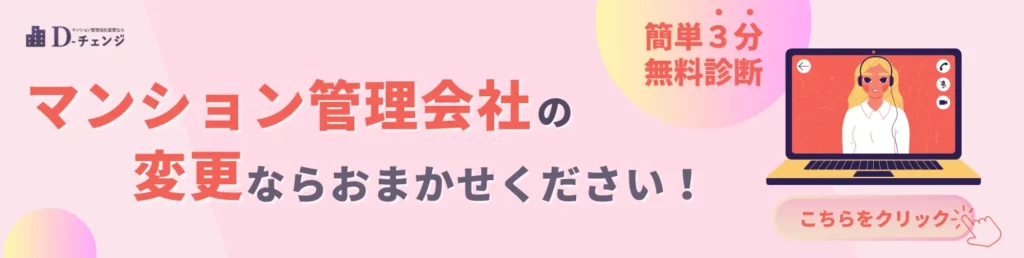【要確認】特定建築物定期調査の対象になるマンションとは?
「うちのマンションって定期調査の対象なのかな?」
「調査しないと何か罰則があるの?」
こうした疑問に答える記事です。
この記事でわかること
- 特定建築物定期調査の対象になるマンションの条件
- 調査が必要になった場合の具体的な対応方法
- 調査を怠ったときに発生する罰則やリスク
特定建築物定期調査は、建築基準法に基づき、一定の規模を超えるマンションに義務づけられた建物点検です。対象となるかどうかは、階数や延床面積によって決まります。
もし対象にもかかわらず調査をしなかった場合、行政からの指導や過料、さらには事故が起きた際に責任を問われることもあります。
初めて聞く制度で不安になりますよね?
でも、必要な条件や調査の流れを事前に把握しておけば、慌てずに対応できます。
この記事を読むことで、ご自身のマンションが調査対象かどうかを確認でき、必要な対応やリスク回避の方法も整理できます。
安心して住めるマンション管理のために、最後まで読んでみてください。

この記事の監修者
株式会社デュアルタップコミュニティ 代表取締役社長
池田 秀人
2017年6月株式会社デュアルタップ入社、2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、完全子会社へ(取締役就任)、2019年7月専務取締役に就任、2020年7月代表取締役に就任~現在に至る
所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
目次
特定建築物定期調査とは?

特定建築物定期調査(通称「12条点検」)は、建築基準法第12条に基づく調査・検査です。この法律により、特定建築物の所有者・管理者は、建物の敷地・構造・設備を定期的に調べる義務があります。そして、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
調査は主に以下の4種類に分けられています。
- 特定建築物定期調査
- 防火設備定期検査
- 建築設備定期検査
- 昇降機定期検査
これらのうち「特定建築物定期調査」は、多くの人が利用する特定建築物を対象とする調査です。利用者の安全確保を第一の目的として行われるものとなります。
特定建築物定期調査の対象となる建物とは?

対象用途(建築物の種類)
以下の用途を持つ建築物が対象となります。
- 学校・体育館・病院・診療所・劇場・映画館・集会場
- 百貨店・マーケット・遊技場・カラオケ店などの商業施設
- 旅館・ホテル・飲食店・サービス業店舗
- 共同住宅(マンション含む)・寄宿舎・下宿
- 展示場・博物館・図書館・公衆浴場・自動車車庫 など
規模の条件(床面積・階数)
上記用途の建物のうち、次のいずれかに該当するものが調査対象です。
| 条件項目 | 対象となる目安 |
| 階数 | 3階建て以上 |
| 延べ面積 | 1,000㎡以上(約302坪) |
| 特別用途 | 高齢者施設、病院、宿泊施設などはさらに条件が緩和される場合も |
共同住宅(マンション)の場合
マンション(共同住宅)も対象になりますが、すべてが対象ではありません。
対象となるマンションの一例
- 3階建て以上で延べ床面積が1,000㎡(約30戸前後)を超える場合
- 店舗付きマンションや併用住宅で多数の利用者が出入りする場合
特定建築物定期調査の費用相場

特定建築物定期調査にかかる費用相場を、以下の表にまとめました。
| 延床面積 | マンション | 事務所ビル | マンション以外の建築物 |
| 〜1,000㎡ | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 |
| 1,001〜2,000㎡ | 40,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
| 2,001〜3,000㎡ | 50,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
費用は、建物の延床面積と種類によって変動します。一般的に、延床面積が広くなるほど、調査費用も高くなる傾向があるでしょう。また、マンションは病院や複合施設といった他の建築物より、比較的安価なことが多いです。
ただし、表に示した金額はあくまで目安と考えてください。実際の費用は調査会社ごとに異なるため、参考情報として捉える必要があります。正確な費用をお知りになりたい場合は、複数の調査会社へ見積もりを依頼しましょう。
特定建築物定期調査の実施対象や運用方法は、各地方自治体によって異なります。
たとえば、東京都では調査が義務づけられていますが、その他の地方自治体では一部対象外の場合があります。
必ず、お住まいの自治体の建築指導課などに確認してください。
対象マンションが行うべき具体的な対応

誰が調査義務を負う?(所有者・管理組合・管理会社)
特定建築物定期調査の実施義務は、原則として建物の所有者または管理者にあります。
分譲マンションでは、管理組合が実質的な責任主体となるケースが多く、管理会社が実務を代行する形が一般的です。
自主管理の場合は、管理組合自身が調査業者の選定・報告まで行う必要があります。責任の所在を明確にし、放置せずに早めの対応が重要です。
調査の頻度とタイミング
特定建築物定期調査は、概ね3年に1回の頻度で実施が求められます(地方自治体によって異なる場合があります)。
また、建物の規模や用途によって調査時期が指定されるケースもあるため、市区町村からの通知には必ず目を通しましょう。
調査期限を過ぎると行政指導や罰則の対象になるため、管理スケジュールに組み込んでおくことが重要です。
調査の流れ(準備〜報告書提出まで)
- 対象建築物の確認(市区町村の情報確認)
- 有資格者(建築士など)への調査依頼
- 現地調査の実施(外壁・避難経路・共用部の安全点検など)
- 調査結果のとりまとめ(報告書作成)
- 所轄自治体への報告書提出
調査は事前準備とスケジュール調整が肝心です。報告書には写真や劣化箇所の記録も必要なため、専門業者と連携して正確かつ適切に進める必要があります。
違反した場合の罰則やリスク

行政指導・命令・過料の可能性
特定建築物定期調査を怠ると、建築基準法第101条に基づき、所管行政庁から指導・報告命令・立入検査などの行政処分が行われる可能性があります。
さらに、調査結果の未提出や虚偽報告を行った場合、50万円以下の過料が科されることがあります(建築基準法第101条第1項・第4項)。
これは、建物利用者の安全を確保するために厳しく定められており、法令遵守が求められます。
事故が発生した場合の責任(管理組合のリスク)
定期調査を怠った結果、外壁の落下や避難経路の不備などが原因で事故が発生した場合、管理組合や所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。
また、保険で補填できないケースや、社会的信用の失墜も深刻なリスクです。マンションの資産価値や住民の安全を守るためにも、法定点検は確実に実施すべきです。
まとめ
最後に、この記事の内容を振り返っておきましょう。
- 特定建築物定期調査は、建築基準法第12条に基づく法定点検です
- 対象となるマンションは、3階建て以上かつ延べ面積1,000㎡以上が目安です
- 調査の実施義務は、所有者または管理組合にあります
- 概ね3年に1回の頻度で調査し、所轄の自治体へ報告が必要です
- 未実施の場合は、行政指導や過料、損害賠償責任のリスクがあります
もし「自分のマンションが対象か不安」という場合は、まず延べ面積や階数を確認してみてください。不明な場合は、管理会社や自治体に相談するのが安心です。
制度を知らずに放置すると、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。早めに確認し、必要な調査はきちんと対応しておきましょう。
特定建築物定期調査を通じて、住まいの安全と価値を守っていきたいですね。