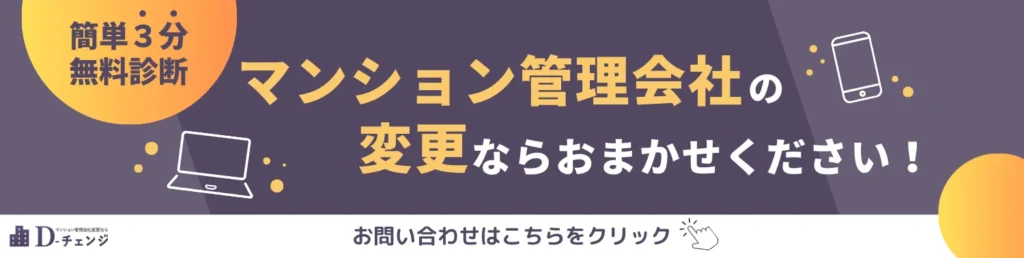管理業者管理者方式とは?仕組み・メリット・注意点まで6つの基本解説
「管理業者管理者方式ってよく聞くけど、どんな仕組み?」
「マンション管理で失敗したくないけど、選び方が分からない…」
そんな疑問を持つ方に向けて、本記事では「管理業者管理者方式」の基本的な特徴や他方式との違い、メリット・デメリット、導入時の注意点などを6つの視点でわかりやすく解説します。
では、住民にとって本当に安心できる管理体制とは何でしょうか?
判断材料を整理して、自分たちのマンションに合った運営方法を考えていきましょう。

この記事の監修者
株式会社デュアルタップコミュニティ 代表取締役社長
池田 秀人
2017年6月株式会社デュアルタップ入社、2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、完全子会社へ(取締役就任)、2019年7月専務取締役に就任、2020年7月代表取締役に就任~現在に至る
所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
目次
管理業者管理者方式を理解するための3つの基本知識

「管理業者管理者方式」とは、どのような仕組みなのでしょうか。まずは、他方式との違いや制度の概要を理解しましょう。
以下の3つの視点からわかりやすく解説します。
- 管理業者管理者方式の仕組みと特徴
- 他方式との違い(外部管理者方式・第三者管理者方式)
- 導入状況と今後の見通し
管理業者管理者方式の仕組みと特徴
管理業者管理者方式とは、管理会社の社員が理事長を務める運営形態を指します。
通常、マンションでは住民の中から理事長を選出しますが、この方式では管理会社が運営の中心を担うため、住民の負担を大きく減らせる点が特徴です。
とくに、高齢化が進んだマンションや、役員のなり手が見つかりにくい小規模物件などで導入が進んでいます。
外部管理者方式との関係性
また「管理業者管理者方式」は、より広い分類である「外部管理者方式」の一種です。
住民以外が理事長を担うスタイルの総称が外部管理者方式であり、実際には複数の形態が存在します。
たとえば、外部の専門家や弁護士などに理事長を委任する「第三者管理者方式」や、管理会社の社員が理事長となる「管理業者管理者方式」などが含まれます。
関係性を整理すると、次のようになります。

図のように、外部管理者方式の中に第三者管理者方式があり、管理業者管理者方式はその一形態です。任せる主体や範囲によって区別されています。
導入状況と今後の見通し
国土交通省の2024年調査によると、住民以外が理事長を務める「外部管理者方式」を導入している管理組合は、全体の約32%にのぼります。
背景には、管理の担い手不足や高齢化、住民の関心低下といった課題があります。
とくに、小規模マンションや賃貸化が進んだ物件では、理事会の運営自体が難しく、管理の専門家に一任するニーズが高まっているのが現状です。
こうした状況をふまえると、この方式を選択するマンションは今後も増加傾向が続くと見込まれます。
関連記事:マンション管理組合の業務の委託とは?委託するメリット・デメリットについても解説
国のガイドラインに基づく導入時の注意点
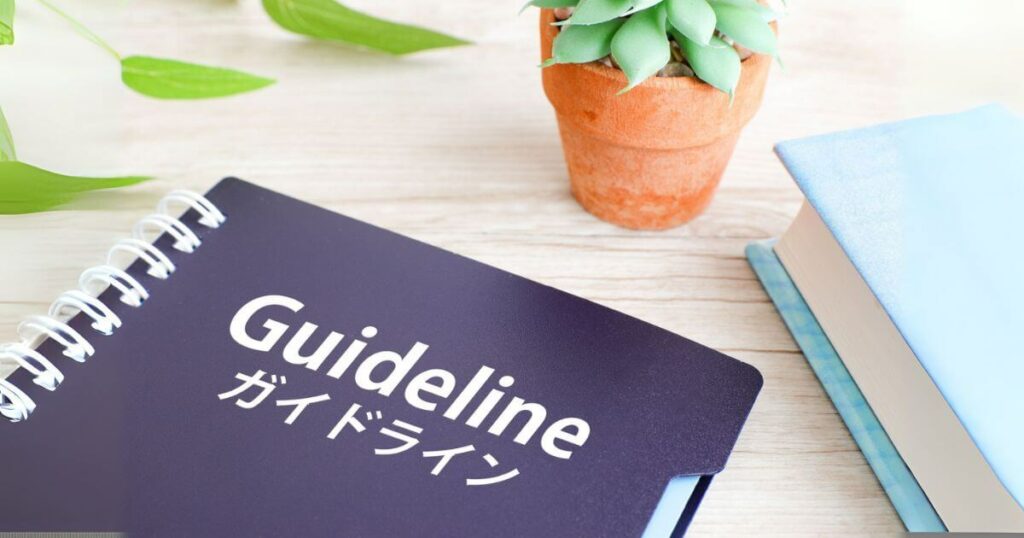
管理業者管理者方式を導入する際は、透明性の確保とトラブル防止が欠かせません。
そのため、国土交通省は「マンション管理適正化指針」などで、以下のような点に注意するよう示しています。
| 注意点 | 内容例 |
| 情報開示 | 議事録や決算報告などを住民に適切に共有すること |
| 利害関係の排除 | 管理会社が自社に有利な発注を行わないよう、監視体制を整備すること |
| 会計の分離 | 組合の資金や印鑑を管理会社と分けて管理すること |
| 外部監査の活用 | 第三者によるチェック体制を導入することが望ましい |
管理を任せている場合でも、住民が情報を把握しておくことは大切です。管理する側がきちんと説明できる体制を保つことで、安心して暮らせる環境が長く続きます。
関連記事:【9割が知らない】マンション管理会社と管理組合の関係とは?
管理業者管理者方式のメリットとデメリット
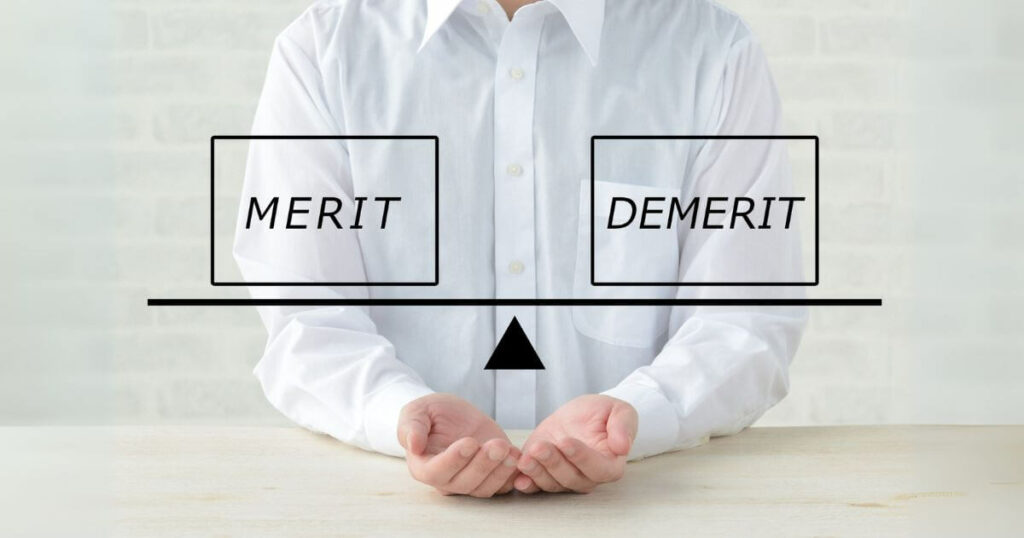
管理業者管理者方式には、住民の負担を減らせるという利点がありますが、気をつけたい点もあります。メリットとデメリットを知っておくことで、管理方式の選定に役立つでしょう。
以下の3つの観点から、本方式のメリットとデメリットを整理します。
- 理事会の負担軽減と専門性の活用(メリット)
- 費用や透明性への懸念(デメリット)
- 導入・継続時に気をつけたいポイント
メリット|理事会の負担軽減と専門性の活用
管理業者管理者方式の最大の魅力は、住民の負担が大幅に減ることです。
理事長の役割を管理会社の社員が担ってくれるため、住民自身が会議を仕切ったり、業務を調整したりする必要がありません。
さらに、管理会社は法令や建物管理に精通したプロフェッショナルです。修繕計画や業者選定なども専門的に対応してくれるため、安心して任せられます。
「理事をやりたくない」「高齢で難しい」「忙しくて関われない」といった悩みを持つマンションでは、とくに有効な方式といえるでしょう。
デメリット|費用や透明性への懸念
一方で、すべてを管理会社に任せることには、いくつかの注意点もあります。
まず、理事長の報酬や業務代行の対価がかかるため、管理費が高くなる傾向があります。他の方式と比べて、住民の負担が増えることもあるでしょう。
また、運営を外部に一任することで、透明性が損なわれるリスクもあります。
たとえば、管理会社が特定業者と結びつき、高額な工事契約が行われてしまうかもしれません。
さらに、住民の確認や監視が不十分だと、帳簿の開示が曖昧になったり、意思決定が独断的に進んだりするおそれもあります。
こうした問題を防ぐには、住民も日ごろから管理状況に目を向け、一定の関わりを持つことが大切です。
導入・維持で気をつけたいポイント
管理業者管理者方式では「任せきりにしないための住民の関与姿勢」が大切です。理事会がない場合でも、総会での報告や確認は欠かさないようにしましょう。
会計の透明性や契約内容の妥当性についても、住民から管理会社に対して適宜確認する必要があります。
また、第三者監査役や外部専門家の活用も、運営の健全性を保つうえで効果的です。
信頼を前提に、適度な距離感で関与することが、安心して暮らし続けるための支えになります。
関連記事:マンション管理会社への管理委託費用の相場とは|委託するメリット・デメリットも解説
安心して導入するためのチェックポイント

「任せたはずなのに、思っていたのと違った」そんな不満を抱く方も少なくありません。
しかし、導入前にいくつかのポイントを確認しておけば、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。信頼できる管理体制を築くために、事前に確認しておきましょう。
確認しておきたい主なポイント
- 管理費の使途と情報開示のチェック
- 利益相反を防ぐ体制の整備
- 導入前に確認すべき4つの確認項目
管理費の使途と情報開示の確認ポイント
管理業者管理者方式では、住民が理事会を直接運営しないため、管理費などの資金の流れが見えづらくなります。
とくに理事長が管理会社の社員の場合、支出の妥当性や契約内容が住民に十分に開示されないまま進んでしまうこともあるのです。
たとえば、高額な見積もりによる工事契約や、特定の業者との癒着により、不透明な支出が繰り返されてしまうおそれもあります。
こうしたトラブルを防ぐには、年次総会や報告会で内容をしっかり確認し、疑問点はその場で質問する姿勢が大切です。
任せていても、資金の動きは住民全体で把握できる状態が望ましいでしょう。
利益相反を防ぐための体制づくり
管理会社が理事長を兼ねる場合、意思決定と実務が同じ組織に集中するため、利益相反の懸念がつきまといます。
特定業者との不透明な取引や、割高な工事契約といった問題が実際に起こる可能性も否定できません。
加えて、理事会がない体制では、住民の声が制度的に届きにくくなるという課題もあります。
こうしたリスクを防ぐには、外部監査役の導入や、住民有志によるチェック体制の整備が有効です。
「任せているからこそ、監視体制が必要である」という視点を忘れないようにしましょう。
導入前に確認したい4つのチェック項目
管理業者管理者方式を導入する前に、次のような点を確認してきましょう。トラブルの予防に効果があります。
| 確認項目 | 確認方法の例 |
| 会計報告の透明性 | 総会で収支報告が詳細に説明されているか |
| 業者選定の経緯 | 競合見積もりを取ったかどうか、説明があるか |
| ガイドラインや契約内容の明示 | 住民に公開されており、内容が分かりやすいか |
| 意見・要望の伝達手段 | 意見箱や定期アンケート、住民集会などが用意されているか |
これらの項目を事前に確認し、住民間で共有しておくことで「そんなつもりではなかった」といった行き違いを防ぎやすくなります。
安心して暮らせる環境を守るためにも、住民同士の信頼関係と明確なルールの共有が欠かせません。
管理業者管理者方式における役割分担のポイント

管理業者管理者方式では、理事会のあり方や管理会社の業務範囲が大きく変わります。役割を正しく理解しておくことで、安心して管理を任せることができるでしょう。
ここでは、次の3つの視点から管理体制の全体像を整理します。
- 理事会の立ち位置と負担の変化
- 管理会社が担う業務の範囲
- 住民が把握しておくべきこと
理事会の役割がどう変わるか
管理業者管理者方式では、理事会がなくなるか、あっても名ばかりの形になることがよくあります。
これは、管理会社の社員が理事長を務めるため、住民から選ばれる理事がマンションの運営に深く関わらなくなるからです。
その結果、住民の立場は「判断する側」から「承認する側」へと変わります。負担は軽くなりますが、意思決定に関わる機会が減る点には注意が必要です。
管理会社が担う具体的な業務
管理業者管理者方式では、管理会社が理事長を兼ね、次のような業務を包括的に担うのが一般的です。
- 年間予算の作成や会計処理
- 修繕工事や点検業者の選定・手配
- 総会の開催準備や住民対応全般 など
運営方針の決定から日常業務までを一手に引き受けることで、スムーズで効率的な管理が可能になります。
ただし、権限が集中しやすくなる分、不透明な運営を防ぐための監視体制が不可欠です。
住民が知っておくべき基本事項
管理を任せる体制であっても、住民一人ひとりが「何が・誰によって・どう決められているのか」を最低限把握しておく必要があります。
総会の開催時期、修繕の方針、費用の決定プロセス、管理会社の変更条件といった、基本的な情報は事前に確認しておきましょう。
また、住民同士で情報を共有し合うことで、見落としや行き違いを防ぐことにもつながります。
制度に頼るだけでなく、住民自身が関心を持って理解しようとする姿勢が、長期的に安心できる管理体制を保つための土台になります。
関連記事:マンション管理の「第三者管理方式」とは|導入するメリット・デメリットを解説
導入に向いているマンションと管理会社選びのコツ

導入するか迷うときは、どんな物件に向くか、誰に任せるかの2本柱で考えましょう。ここでは次の3点を紹介します。
- 向いているマンションの特徴
- 管理会社の選び方
- 導入後の見直しの可否と注意点
管理業者管理者方式が適しているマンションとは
管理業者管理者方式は、住民だけでの運営が難しい物件に相性が良いです。
たとえば以下のようなケースです。
- 高齢化が進み、理事を担える人が少ない
- 賃貸化が進み、居住者の関心や参加意欲が低い
- 小規模で理事会の構成が難しい
- なり手不足が原因で運営が滞ったことがある
こうした場合は、理事長業務まで含めて管理会社に任せることで、安定した運営が期待できます。
一方で、住民の関与を重視したいマンションには合わない場合もあるため、任せる範囲のバランスは慎重に見極めてください。
管理会社の選び方とチェックポイント
管理業者管理者方式では、管理会社に権限と責任が集中します。
どこに任せるかが将来を左右するので、契約前に以下を確認しておくと安心です。
| 確認項目 | 内容の例 |
| 実績と評判 | 同規模・同地域での管理実績は十分か |
| 情報開示の姿勢 | 会計報告や議事録を住民に分かりやすく共有しているか |
| 担当者の対応 | 契約前から丁寧で誠実な対応があるか |
| 契約内容の明確さ | 管理範囲や報酬が事前に明文化されているか |
任せたあとに揉めないためにも、契約前の比較検討は欠かせません。
導入後の見直しは可能か(変更時の注意点)
結論、見直しは可能ですが容易ではありません。
理事会方式へ戻すには、総会での特別決議(通常は4分の3以上の賛成)、新たな理事長候補の確保、管理契約や規約の見直しなど、複数の手続きが必要になります。
時間と労力がかかるため「ダメなら戻せばいい」前提での導入は危険です。
将来の理事候補が確保できそうか、管理会社と長期的な信頼関係を築けるか、この視点で落ち着いて判断しましょう。
関連記事:【保存推奨】マンション管理組合とは?担う役割やよくあるトラブルについて詳しく解説
まとめ|管理業者管理者方式を選ぶ前に知っておきたいこと

管理業者管理者方式は、マンション運営の負担を大幅に軽減できる一方、すべてを任せきりにするとリスクを見落としやすい管理形態です。
とくに理事長の役割まで管理会社に委ねるため、意思決定の透明性や情報共有のあり方が、運営の満足度を大きく左右します。
本記事では、次の観点からポイントを整理しました。
- 管理業者管理者方式の仕組みや他方式との違い
- 住民の関与が少ないことによるメリットと注意点
- トラブルを防ぐ監視体制や契約チェックのポイント
- 導入に向いているマンションの特徴と管理会社選びの視点
この方式が適しているかどうかは、住民の構成や理事会体制、信頼できる管理会社の有無によって異なります。
導入を検討する際は「任せられるか」ではなく「安心して任せ続けられるか」という視点を持ち、長期的な見通しのもとで慎重に判断しましょう。